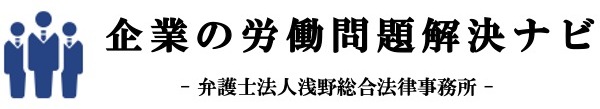団体交渉当日の進め方・話し方についてポイントを解説していきます。団体交渉の事前準備をきちんと終えたら、いよいよ設定した日時に団体交渉を行います。
団体交渉は、労使交渉のなかでも、通常の話し合いではありませんし、雑談でもありません。コツをおさえて発言することが、企業のリスク軽減につながります。
本解説では、団体交渉の当日に、実際の交渉の現場でどのように話したらよいか、どのように進行したら良いかについて解説します。なお、不安なときは、団体交渉を数多く経験した弁護士のアドバイスを聞き、労働組合、特に合同労組(ユニオン)の行う団体交渉の一種独特な雰囲気をあらかじめ知っておくことが有益です。
まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用
まとめ 団体交渉の対応手順
↓↓ 動画解説(約12分) ↓↓
団体交渉は、普通の話し合いではない
労働組合、特に、合同労組(ユニオン)との団体交渉の進め方、話し方を理解するにあたって最も重要なことは、「団体交渉は、普通の話し合いではない」という点を理解することです。「交渉」という言葉から想像する以上に、議論が白熱し、あらっぽいやり取りとなることがありますし、労働組合が保護されていることから不利な状況からのスタートとなるためです。
一方で、特別な場だと気負い過ぎてしまうと失敗することもあるため注意が必要です。
誠実に交渉する
労働組合には、労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)が保障されているため、会社は、労働組合から申し入れられた団体交渉について、誠実に交渉することが義務付けられています(使用者の誠実交渉義務)。
そのため、合同労組(ユニオン)が、荒っぽい交渉のやり取りをしてきたり、一般常識に反する話し方や態度、人として失礼な態度をとることがあったとしても、やり返すのではなく、淡々と対応し、接する必要があります。会社側が同様に無礼な態度に徹すれば、団体交渉拒否の不当労働行為として違法になってしまうおそれがあるからです。
労働組合から暴言・罵倒を受けたときの話し方
団体交渉は、あくまで話し合いの場であって暴力の場ではありません。良識があり、労働問題の解決を第一とする労働組合であれば、暴言・罵倒・罵声といった非常識な行為はしないはずです。しかし、合同労組(ユニオン)の中には、残念ながら、会社の不誠実な態度という言いがかりをつけ、暴言を吐いたり罵倒したり、罵声・怒号を浴びせてくる団体があります。
組合側の主張がたとえ正しいものだったとしても(そして、会社側の主張が間違ったものだったとしても)、それはそれとして、交渉態様として、人格否定の発言をしたり大声を張り上げたり、机を叩いて相手を威嚇したりする態度は、誠意あるものとは到底いえません。
したがって、万が一にも労働組合側が暴力的な手段に出て、生命・身体の危険を感じるときは、ただちに団体交渉を中止するようにしてください。そして、今後も改善がない場合には次回の団体交渉を行わず、団体交渉を打ち切る旨を書面で組合に警告するようにします。
このとき、会社側は誠意ある対応をしており、組合側の交渉態度が悪質な点が原因であることを証拠化するため、録音をしておくようにしてください。
なお、当然ながら、感情が高ぶって会社側の参加者が暴言を吐いたり暴力的な手段をとったりすることは控えてください。

労働組合がよく使う発言に対抗するための話し方
団体交渉では、通常の交渉とは異なり、憲法・労働組合法による法的保護を受けた労働組合という団体との特殊なやり取りです。このやり取りの中では、合同労組(ユニオン)は何度も会社との交渉を経験していることから、よく使われるテクニック、ノウハウを確立しています。
団体交渉は話し合いの場であり、組合と会社との双方向的なやり取りが重要なため、労働組合がよく使う発言を知り、それらの発言ごとに、どのように切り替えしたらよいか、その話し方、対応方法を理解しておくことが大切です。
「労働委員会に不当労働行為救済申立てをする」
会社が申し入れられた団体交渉を放置したり無視したり、団体交渉に応じないという決断をしたりするとき、労働組合から「団体交渉拒否の不当労働行為だ」という発言を受けることがあります。
不当労働行為は、不利益取扱い、団体交渉拒否、支配介入の3種類があります。いずれも会社が組合を敵視して不利益な処分をし、組合の権利を侵害することを防止するために違法であることが労働組合法で定められた行為類型です。不当労働行為にあたるとき、都道府県労働委員会における不当労働行為救済申立事件によって争われ、救済命令が下されると、その処分の撤回や損害賠償等、会社にとって不利益な措置が命じられます。
ただ、団体交渉において不当労働行為を指摘し、会社を萎縮させようとするのは労働組合側の常套手段のため、不当労働行為だといわれたからといってひるんではなりません。むしろ、このような発言を多用する組合と対峙するときには、労働委員会で中立公正に判断してもらったほうが解決がスムーズなケースもあります。

「労働基準監督署に告発する」
団体交渉の議題となった労働問題が、ある労働者と会社間の問題、つまり、個別労使紛争の解決であったとき、会社が組合側の要求を受け入れないと「労働基準監督署に告発する」と発言されることがあります。
確かに、労働基準法、労働安全衛生法等に違反しているとき、会社は法令違反を是正する必要があります。ただ、労働基準監督署が管轄するのは、労働基準法、労働安全衛生法等、労働者の最低限の権利を守るための法律のうち、特に重大なものとして刑事罰による制裁の対象となっている違反のみです。
そのため、法令違反の指摘を受けたらよく検討し、是正を図ることで足り、労働基準監督署への告発を過度におそれる必要はありません。きちんと是正を図っていれば、労働基準監督署の立入り調査を受けたとしても「現在是正中である」と回答すればよく、適切に対応していればそれ以上に追及を受けることは通常ありません。
「ビラまき・記者会見をする」
労働組合は、団体交渉で要求を通すためのプレッシャーとして、団体交渉で話し合っている問題を社外の第三者に広めようとしてきます。社外の第三者に労働問題があることを知られてしまえば、業務に支障が生じたり、会社の名誉・信用が傷つけられ、企業価値が下がってしまうことが予想されるからです。
「ビラまきする」、「記者会見をする」といった発言は、そのような意図でなされます。
しかし、会社に特に法令違反がないのであれば、社外に知られてしまうことを過剰に恐れては組合の思うつぼです。そのため、「ビラまき・記者会見する」といった発言をおそれてはなりません。このことからも、団体交渉を行う前に、事前準備の段階から、社内の労働問題を是正しておくことの重要性をご理解ください。

「ストライキ(争議行為)をする」
労働組合に認められた労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)のうち、最終手段にあたるのが団体行動権(争議権)です。つまり、労働組合には、ストライキ(争議行為)をする権利が認められています。
そのため、労働組合が団体交渉で、「ストライキ(争議行為)する」と発言し、会社にプレッシャーをかけてくることがあります。
しかし、労働組合にとってもストライキ(争議行為)には費用と手間がかかるため、団体交渉における話し合いで解決できるのであればそのほうがよいと考えているはずです。特に、合同労組(ユニオン)の団体交渉にありがちな、個別労働紛争の解決を目指す戦いでは、対象となっている組合員としても、ストライキ(争議行為)して会社にダメージを与えることより、自身の問題解決を優先したいという気持ちがあります。
労働組合の思い通りにならないがために、「ストライキ(争議行為)する」という発言を招いたのであれば、会社側の団体交渉対応に、違法な点がないか注意しておきましょう。

団体交渉の進め方(進行方法)のポイント
団体交渉を申し入れられた会社のほとんどが、団体交渉対応が初めてであり、労働組合対応になれていません。そのため、多くの団体交渉では、労働組合側(特に、合同労組(ユニオン)の役職者や上部団体の参加者)がリードして議論を進めていくことが通例です。
しかし、労働組合側の要求から始める交渉であるとはいえ、議論をすべてリードされていては、言うなりに進行され、思いもよらない不利益を受けるおそれがあります。そこで次に、団体交渉をどのように進めていけばよいか、団体交渉の進め方(進行方法)のポイントを解説します。
なお、具体的にどのように進めたらよいか、申入れから解決までの流れを知りたい方は、「団体交渉の対応手順」をご覧ください。
労働組合の要求からはじまる
団体交渉は、労働組合側が申し入れてくる交渉です。そのため、会社側が検討すべきことは、「労働組合の申入れに応じるかどうか」、「労働組合の要求を受け入れるかどうか」です。つまり、会社側は「労働組合の要求」を特定し、その是否を検討すればよいのであって、それ以上の対応をする必要はありません。
団体交渉の開始は、労働組合による団体交渉申入書の送付によって始まります。申入書に記載された議題・要求を事前準備の段階でよく検討し、回答を考えておかなければなりません。そして、しっかり準備をしていたときには、団体交渉の席上でそれ以上の要求をされても、回答を拒否し、次回までの課題として持ち帰り検討することで足ります。
粘り強く交渉を続ける
団体交渉での話し合いを行うとき、会社側は途中であきらめてはなりません。
労働組合の要求を受け入れる必要は必ずしもないですが、途中で心が折れて、やけっぱちになってしまえば、団体交渉は労働組合の有利に進みます。ただでさえ、労働組合は憲法・労働組合法による法的な保護を受け、会社側としては不利な状況からのスタートとなりがちなのですから、交渉は時間をかけてじっくりと行わなければなりません。
労使の要求があまりにかけ離れてみえても、団体交渉の回数を重ね、議論を続けることで、最終的には会社側にも納得のいく和解で落ち着くケースも少なくありません。
話し合いは「双方向」
団体交渉は、話し合いの場ですから、コミュニケーションは双方向となるのが基本です。決して、労働組合が一方的に会社の責任追及をしたり、糾弾して追い詰めたりする場ではありません。
合同労組(ユニオン)の中には、一方的に要求を突きつけ、発言は組合からの質問に回答するだけにするよう強く求めてくる団体がありますが、団体交渉の趣旨を履き違えていると言わざるを得ません。労働組合の要求に不明確な点、疑問点があるときは、会社側からも組合側に対して質問することで、団体交渉における話し合いをより実益のあるものにすることができます。
団体交渉の席上で約束しない
団体交渉の内容は、労働組合側によって録音や議事録等の方法で記録されています。そのため、団体交渉の席上での発言はすべて「記録されている」ことを念頭に置いて慎重に行うようにし、不用意な発言は避けてください。
そして、団体交渉の席上で、思いつきで労働組合と約束ごとを交わしてはなりません。労働組合とした約束は、たとえ口約束であれ、今後の団体交渉に大きく影響します。
特に団体交渉の場で、労働組合が出してきた書面には注意してください。労働組合との間で文書による合意をすると、その文書の題名にかかわらず「労働協約」という強い効果を持つ書面となり、今後の労使関係を縛る可能性があります。
なお、その他に、団体交渉においてやってはいけない禁止事項は下記解説をご参照ください。
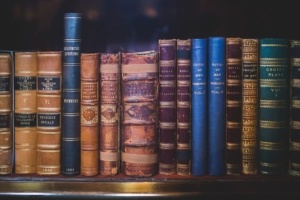
↓↓ 動画解説(約10分) ↓↓
団体交渉の発言者を決める
団体交渉で、いろいろな人が、思いついた順に発言していると、収集がつかなくなってしまいます。話し合いが混乱すれば、少なくとも会社側に有利にははたらきません。
団体交渉の場が荒れると、感情的になって、暴言、不適切発言に及ぶおそれもあります。
団体交渉で、会社側で発言をするとき、その発言者を事前に決めておきましょう。会社側に有利な発言のできる「証人」は、事実・争点ごとに限定しておくと、なおよいでしょう。誰が発言するのが最も良いかを事前に検討した上で参加者を決める必要があります。
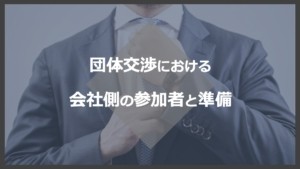
まとめ
今回は、団体交渉の席上での会話や進行の方法について、解説しました。団体交渉当日の対応には、法律上の明確なルールがなく、裁判例等にも記載されないような細かなテクニック、ノウハウを駆使しなければなりません。
労働組合を無視、放置してはならず、かつ、労働組合の言うなりになってはなりませんが、一方で、強気で押していくだけではリスクが大きく、バランス感覚のとれた臨機応変な対応が必須です。団体交渉拒否の不当労働行為といわれるような不誠実な対応とならないよう、他方で、会社にとって不利にならないよう適切な対応が大切です。
当事務所の団体交渉サポート
弁護士法人浅野総合法律事務所では、企業の労働問題解決を勝ち取った経験が十分にあります。
交渉相手となる合同労組(ユニオン)は交渉のプロで、豊富な交渉経験から培ったテクニックで、会社が気づかぬうちに不利な状況に追い込まれるよう仕向けてきますから、対抗するためにはこちらも弁護士のアドバイスが重要です。お気軽にお申し付けください。
団体交渉についてよくある質問
- 団体交渉で労働組合から厳しい追及を受けたら、どう話したらよいですか?
-
団体交渉で労働組合から受ける「不当労働行為である」との指摘、「労基署へ告発する」といったよくある発言には、労働法の知識をよく理解して対応しなければなりません。もっとよく知りたい方は「労働組合がよく使う発言に対抗するための話し方」をご覧ください。
- 団体交渉をどのように進めたらよいですか?
-
団体交渉の進め方では、団体交渉が単なる話し合いではないことを理解し、組合の権利に意識しながら、双方向的に粘り強く話すことが大切です。もっと詳しく知りたい方は「団体交渉の進め方(進行方向)のポイント」をご覧ください。
- 相手方のことを理解する
合同労組(ユニオン)とは?
誠実交渉義務とは - 団体交渉の申入れ時の対応
労働組合加入通知書・労働組合結成通知書の注意点
団体交渉申入書のチェックポイント - 会社側の事前準備と回答書作成
団体交渉の事前準備
会社側が回答書に書くべきこと - 参加者の選定と心構え
会社側の参加者・担当者は誰が適切か
参加する会社担当者の心構え
団体交渉に弁護士が参加・同席するメリット - 団体交渉当日の対応
団体交渉当日の進め方・話し方
やってはいけない禁止事項 - 団体交渉の解決までの流れ
解決までにかかる期間
団体交渉の打ち切り方 - その他
派遣先の団体交渉応諾義務