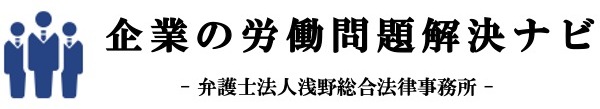チェックオフとは、会社が、賃金から組合費を控除することとする、労働組合との約束ごとです。チェックオフについて定めた労使協定が、チェックオフ協定です。
チェックオフは労使の合意によるものなため、会社は拒否することができます。むしろ、チェックオフを認めることは、会社が労働組合を承認したことを意味し、経済基盤が強固となる等の強い保証を与えることとなります。そのため、チェックオフを求められたとき、会社側は慎重に対応しなければなりません。
今回は、チェックオフ協定とはどのよなものか、組合からチェックオフを要求されたときの会社の適切な対応といった法律知識を解説します。
まとめ 団体交渉の対応を弁護士に依頼するメリット・依頼の流れと、弁護士費用

チェックオフとは
チェックオフは、会社が労働組合との間で労使協定を結ぶことで、組合員からの委託を受け、組合員である社員の給与から組合費を控除して徴収し、一括して組合に納入する制度です。チェックオフの際に結ばれる労使協定が、チェックオフ協定です。
チェックオフは、会社の労働組合に対する便宜供与の1つです。便宜供与は、労働組合の自主性を損なう可能性があり、会社にコントロールされることを防ぐために限定的にしか認められていませんが、チェックオフは、法律の条文には規定されていないものの、便宜供与として認められています。
なお、憲法ないし労働組合法で、労働組合には手厚い保護が与えられていますが、便宜供与を会社に請求する権利はありません。そのため、チェックオフをするかどうかは、労使の合意によって決まります。会社としてはこれを拒否することも自由です。
以下の点で、チェックオフは、かなり例外的な取扱いとなります。
- 労働基準法24条「賃金全額払いの原則」の例外
賃金は全て労働者本人に支払われるべきで、中抜きは許されないという労働者保護のためのルールの例外となります。この例外となるために、労働基準法上、労使協定の締結が必要と定められています。 - 便宜供与の例外
労働組合法では、会社が労働組合をコントロールしないよう便宜供与が限定的にしか認められていませんが、チェックオフは例外的に認められています。 - 支配介入の不当労働行為の例外
会社が労働組合に影響を及ぼそうと働きかけることは支配介入の不当労働行為として違法ですが、チェックオフは例外的に関与が認められます。
労働組合は、自主独立の団体である必要があり、会社との間で労働問題について戦うために、会社に依存してはなりません。そのため、会社から経費援助を受けることは許されません。ただし、チェックオフはあくまでも組合費の徴収について会社の力を借りるだけであって、経費を援助される意味ではないと考えられ、許容されています。
チェックオフは組合を弱体化させるものではなく、むしろ保護し、強化するものであるため、支配介入の不当労働行為にも該当しません。
チェックオフを要求されたときの適切な対応
次に、労働組合からチェックオフを要求されたときの、会社側の適切な対応について解説します。
チェックオフは、会社が労働組合を容認したことを意味し、かつ、組合費の取りっぱぐれを防ぐことができるため、団体交渉の席上等で労働組合からしばしば要求されることがあります。
チェックオフを拒否する
まず、チェックオフは労働組合の権利として認められているものではなく、あくまでも、労使の合意によって決まるものです。また、どのような内容とするかについても、労使協定である程度自由に決めることができます。
そのため、チェックオフを要求されたとき、会社側としては拒否することができます。
特に、敵対的な労働組合に対してはチェックオフという便宜を認める必要はなく、また、社外の合同労組(ユニオン)には会社の社員が多く加入していることはあまりないため認める必要性があまり大きくありません。
チェックオフに応じるときは、労使協定を締結する
チェックオフは、労働基準法24条に定められた賃金全額払いの原則の例外となります。賃金からの中抜を防止して労働者を保護するため、生じた賃金は全額を労働者本人に直接払う必要がありますが、源泉徴収等の一定の例外が認められています。
そして、これらの例外としての控除が認められるためには、条文上、労使協定の締結が必須となります。
労働基準法24条1項
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
労働基準法(e-Gov法令検索)
労使協定は、過半数組合(労働者の過半数で組織する組合)もしくは過半数代表者との間で締結する必要があります。そのため、チェックオフを希望する組合は、基本的には社員の多くが加入している過半数代表者となります。
組合員の同意を取得する
会社がチェックオフを行うためには、労使協定を締結するだけでなく、各組合員の同意を取得する必要があります。
労働組合がチェックオフを求めるときでも、労働組合に加入しながら、組合費に関するチェックオフには反対する組合員がいることもあります。このとき、反対する組合員との間では、チェックオフを行うことができないとされています。同様に、従来行われてきたチェックオフの中止を求める組合員がいたときは、その組合員との間ではチェックオフを中止すべきです。
労使協定は、あくまでも労働基準法の例外を認め、会社がチェックオフすることができるようにするためのものであり、実際のチェックオフの実行には、個々の組合員からの委任が必要だからです。
チェックオフを打ち切ることができるか
一旦はチェックオフを認めたとき、その後の事情の変化に応じてチェックオフを会社から一方的に打ち切ることができるかが問題となることがあります。
労使協定はあくまでも双方当事者の合意であり、労使協定の期限が経過すれば打ち切ることは可能なようにも思えます。しかし、不当労働行為による労働組合の保護がはたらくことから、一旦成立したチェックオフを打ち切ることは、原則として支配介入の不当労働行為にあたり許されません。
チェックオフの打ち切りが、不当労働行為とならないようにするためには、次の点に注意して進める必要があります。
- チェックオフの打ち切りに、労働組合を弱体化させる意図がないか
- チェックオフの打ち切りが、労働組合にとって不利な時期に行われるものではないか
- チェックオフを継続することが、長期の間、慣行になっていないか
まとめ
今回は、チェックオフについての基本的な法律知識と、労働組合からチェックオフを求められたときの会社側の適切な対応について解説しました。
労働組合の希望するチェックオフに応じると、労働組合の地位が強化されます。そのため、労働組合が会社の発展のために協調的なときはチェックオフに応じてもよいですが、会社に敵対的な労働組合とはチェックオフ協定を結ぶべきではありません。
また、チェックオフに応じるときは、チェックオフ協定という労使協定を締結する必要がある点に注意が必要です。